※Word文書をプレビューで表示している場合、表記にズレが生じる可能性があります。
データをダウンロードした際には正しく表記されます。
【総合的な学習の時間】偉人伝から「自分事」へ!4年生 障害者福祉教育の単元展開(塙保己一を導入として)
小学校中学年の総合的な学習の時間(以下、「総合」)は、探究的な学びを深める重要な時間です。特に福祉教育は、子どもたちが社会の一員として共生について考える大切なテーマとなります。
本校では、4年生で「目の見えない人への福祉」をテーマに据えるにあたり、偉人である塙保己一(はなわほきいち)を導入としました。この単元は、単なる偉人伝や福祉の知識習得に留まらず、「なぜそうした工夫が生まれたのか」「自分たちに何ができるのか」という問いを深く追求できる展開を目指しました。
ここでは、その単元構成と具体的な展開の工夫をご紹介します。記事の最後には指導案も載せますので、参考にしていただければ幸いです。
1.単元のテーマと目標
テーマ:偉人・塙保己一に学ぶ「共生」のカタチ
(~目の見えない人へのサポートと社会のバリアフリー化~)
単元の目標(目指す子どもの姿)
- 塙保己一の偉業とその背後にある様々な人々のサポートを知り、協力・共生の意義を考える。
- 視覚障害者の生活における具体的な不便さを理解し、自分事として捉えることができる。
- 社会のバリアフリー化の工夫に関心をもち、目の見えない人への具体的な声かけや行動を考え、実践しようとする。
2.単元全体の流れ(大きな問いの変遷)
本単元のキーポイントは、学習を進める中で、子どもたち自身の「問い」が段階的に発展していくように設計した点です。
| 段階 | 学習の焦点 | 子どもの主な問い(例) | 目指す学びのゴール |
|---|---|---|---|
| A | 偉人・塙保己一を知る | 「塙保己一はどんな人?」「どうして目が見えなくなったの?」「周りの人のサポートはあったのかな?」 | 偉業を支えた「人々の協力」に気づく。 |
| B | 目の見えない人の生活を知る | 「現代の目が見えない人はどんなことに困るのだろう?」「昔と今で不便さはどう違う?」 | 視覚障害者の不便さを具体的に理解し、課題意識をもつ。 |
| C | バリアフリー化と自分たちの行動 | 「その不便さを解消するために社会はどんな工夫をしている?」「私たちにできることは?」 | 行動を伴うアウトプットへ繋げる。 |
3.単元の詳細な展開(全10~12時間程度)
【Part A:偉人探究編】塙保己一の偉業とその背景を知る
| 時数 | 小単元名 | 主な学習活動と指導のポイント | 成果物(まとめ) |
|---|---|---|---|
| A① (3H) | 塙保己一先生について調べよう&疑問を出し合おう |
|
疑問の分類シート |
| A② (2H) | 詳しい人に話を聞こう(ゲストティーチャー等) |
|
ゲストティーチャーへの質問と記録 |
| A③ (3H) | わかったことをまとめよう |
|
塙保己一新聞 等 |
「超人」視点を防ぐ: Part Bへ繋げるため、「目が見えないのにすごい」という「超人視点」で学習が終わらないよう、「目が見えないからこそ」の記憶力や、「周囲のサポートがあったからこそ」の偉業であったことを繰り返し確認します。
【Part B:福祉・共生探究編】現代の課題と工夫を知る
| 時数 | 小単元名 | 主な学習活動と指導のポイント | 成果物(まとめ) |
|---|---|---|---|
| B① (2H) | 目が見えないことの不便さを知る |
|
不便さの洗い出しシート |
| B② (2H) | 目が見えないことの不便さを感じる(疑似体験) |
|
体験の記録と気づき |
| B③ (2H) | 目が見えない人への社会的なサポートを知る |
|
社会のバリアフリー工夫リスト |
| B④ (2H) | 目が見えない人への自分ができるサポートを考える |
|
行動目標シート |
「声かけ」の学びを深化させる: 疑似体験(B②)の際、ガイド役はただ手を引くだけでなく、具体的な状況を伝える「情報提供の声かけ」を意識させることで、「何が安心に繋がるのか」を実感させます。
4.行動を伴うアウトプットへ(単元を締める活動)
単元の最終段階では、子どもたちが考えたことを具体的な行動に繋げるアウトプットを重視します。
【実践例】
- 福祉ポスターの作成:「声をかけることの重要性」を訴えるポスターを校内に掲示。
- 「やさしい声かけマニュアル」の作成と共有: 視覚障害者に限らず、様々な人に配慮した具体的な声かけ例をまとめ、下級生や他学年に発表する。
- 未来の学校のバリアフリー提案: Bの学習で気づいた学校内の不便な点を改善するため、具体的提案をまとめ、学校に提言する。
まとめ
この単元は、過去の偉人から学び始め、現代の課題と向き合い、未来の行動へと繋げるという、「過去-現在-未来」を一貫して探究する構成となっています。
特に「塙保己一の偉業=周囲のサポート」と「福祉の課題=自分たちのサポート」を連動させることで、子どもたちは「共生とは何か」を深く考える機会を得ることができます。
ぜひ、貴校での総合的な学習の展開のヒントにしてください!
指導案を載せます。Word形式なので変更して使用してください。
https://seosei-bank.com/wp-content/uploads/2025/10/小学4年生総合的な学習の時間障害者福祉教育.docx


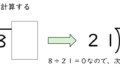
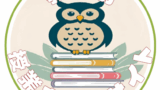
コメント