※Word文書をプレビューで表示している場合、表記にズレが生じる可能性があります。
データをダウンロードした際には正しく表記されます。
― 「なんで学ぶの?」を実感させるための工夫 ―
はじめに:「割合って何に使うの?」という子どもたちの声
5年生で「割合」の単元に入ると、必ずと言っていいほど児童から出てくるのが、
「なんで“割合”を習うの?」
「これって将来使うの?」
という素朴な疑問です。
でも、これこそがチャンスです。“割合”をリアルな生活とつなげてあげることで、学習意欲がぐっと高まるのです。
割合を“自分事”として捉えられる授業アイデアと、単元全体の流れを意識した設計のポイントを紹介します。
1. はじめに「割合探しミッション」
導入の段階で、教科書の問題に入る前に「割合って身の回りのどこにある?」という“割合探しミッション”を出してみましょう。
活動例:
- 食品のパッケージから「脂質の割合」「砂糖の割合」などを探す
- セールの広告を見て「30%OFFは、いくら安くなる?」
- 給食の栄養割合を調べる(たんぱく質、脂質、炭水化物)
→ 生活と直結させることで、児童の関心が一気に高まります。
2. 割合の「3つの視点」を図で見せる
割合では、「もとにする量」「比べられる量」「割合」の関係を理解させるのが大きな壁です。
ここでは、円グラフや図ブロックを用いて視覚的に提示すると、理解が進みます。
図での例:
- ケーキ全体(100%)のうち、友達が食べた割合(40%)
- クラスの男子の人数を“もと”にした割合(例:男子12人、女子18人 → 女子は男子の150%)
→ 教科書だけでなく、図で「割合の向き」を確認する時間をしっかり確保しましょう。
3. 「買い物ごっこ」で使える割合に!
中盤〜後半にかけては、「割合を使って生活に役立てる活動」を盛り込むのがおすすめです。
実践例:「買い物名人になろう!セール商品選びゲーム」
- 架空のチラシを用意し、20%OFF・30%OFF・半額などの商品を提示
- 「1000円持って何がいくつ買える?」「一番お得なのは?」など、計算と判断を両立させる問題を班で解く
→ 「割合を使うと、お金をうまく使える!」という納得感が生まれます。
4. 最後に「自分割合レポート」
単元のまとめでは、児童が自分で考えた“割合問題”や、生活から見つけた“割合の話”をレポート化してみましょう。
レポート例:
- 「この前のお菓子、脂質が30%でびっくりした!」
- 「弟の身長は私の80%だったよ」
- 「家の冷房代、去年より20%下がってた!」
→ これにより、「割合=テストだけのもの」ではなくなるのです。
おわりに:「自分ごと化」が学びを深くする
割合は、抽象的なだけに“意味がわからないまま解ける子”もいれば、“意味がわからなくて止まる子”も多い単元です。だからこそ、「これって自分の生活にも関係してるんだ!」と実感させる設計が重要です。
割合は、子どもたちの暮らしに根ざした数学です。
身近さとリアルさを大切にした授業で、“わかる”と“使える”をつなげてみませんか?


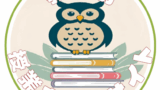
コメント