※Word文書をプレビューで表示している場合、表記にズレが生じる可能性があります。
データをダウンロードした際には正しく表記されます。
算数の学習では、「ある数が特定の数で割り切れるかどうか」を見分ける力が重要です。特に倍数の見分け方は、整数の性質の学習や、分数の約分、公約数・公倍数の理解にもつながります。
以下に、2〜12の数で割り切れるかどうかの簡単な判別方法をまとめました。児童に班活動などで調べさせたり、分類させたりする活動に活用できます。
◆ 割り切れるかどうかの見分け方一覧
| 割る数 | 見分け方(ルール) |
|---|---|
| 2 | 一の位が 0・2・4・6・8(偶数)なら割り切れる |
| 3 | 各位の数の合計が3の倍数なら割り切れる(例:123 → 1+2+3=6) |
| 4 | 下二桁の数が4の倍数なら割り切れる(例:316 → 16は4の倍数) |
| 5 | 一の位が 0 または 5 なら割り切れる |
| 6 | 2と3の両方で割り切れる数(両方のルールを満たす) |
| 7 | 少し難しい:倍数表で慣れるのが近道(例:49, 56, 63など) |
| 8 | 下三桁が8の倍数なら割り切れる(例:1,248 → 248は8の倍数) |
| 9 | 各位の数の合計が9の倍数なら割り切れる(例:729 → 7+2+9=18) |
| 10 | 一の位が0なら割り切れる |
| 11 | 交互に足し引きして差が11の倍数(または0)なら割り切れる(例:2728 → 2-7+2-8 = -11) |
| 12 | 3と4の両方で割り切れる数(両方のルールを満たす) |
◆ 授業中の活動例:班ごとに数の分類をしよう!
<活動の進め方>
- 各班に、数字カード(100〜999程度)をいくつか配布。
- 割る数(2〜12)の担当を決めて、「どんな数が割り切れるか」のルールを考える。
- その数が割り切れる数字カードを集めて分類。
- 最後に班ごとに発表して、他の班と見比べる。
<ねらい>
- 倍数の見分け方を言葉で説明できるようになる。
- 数字の規則性を実感できる。
- 複数のルール(例えば6や12)を組み合わせて考える力を養う。
◆ ポイント
- 7や8、11は難易度が高いため、「表を見て慣れる」「法則を見つけようとする姿勢を評価する」といった工夫が必要です。
- 「6で割り切れるか?」などの複合的な条件では、「2と3で割り切れることを確かめてみよう」と逆算させるのも有効です。
- 実際の生活で使われている数字(時間、日付、買い物の数など)を題材にすると、実感が持てます。


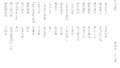
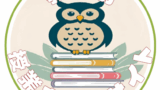
コメント