※Word文書をプレビューで表示している場合、表記にズレが生じる可能性があります。
データをダウンロードした際には正しく表記されます。
みなさんは「ダース」という言葉を聞いたことがありますか?
日本ではあまり日常的に使われませんが、海外では「1ダース」という単位がよく使われます。たとえば、卵を買うときや鉛筆をまとめて買うときなど、「1ダース(12個)」という数え方がされることがあります。
ところで、どうして「10個」や「20個」ではなく「12個」でひとまとめにするのでしょうか?
実は、12という数字がとても便利な数だからです。
例えば、あなたが12個のチョコレートを持っていて、それを友だちと分けたいときのことを考えてみてください。
12個のチョコは、以下のようにいろいろな人数で分けることができます。
- 2人で分けるとき → 1人6個ずつ
- 3人で分けるとき → 1人4個ずつ
- 4人で分けるとき → 1人3個ずつ
- 6人で分けるとき → 1人2個ずつ
- 12人で分けるとき → 1人1個ずつ
このように、12はとても「分けやすい数」なんですね。
一方、10個のチョコレートではどうでしょう?
- 2人で分けるとき → 1人5個ずつ
- 5人で分けるとき → 1人2個ずつ
このように、分けられる人数が限られてしまいます。つまり、12は10よりもたくさんの人数で分けやすい数なのです。
この理由から、昔の人たちは「12」をひとまとまりの単位として便利に使っていたのです。例えば、卵は1パック12個で売られていることが多いですよね? これも「12は分けやすい数だから」という理由があるのです。
学習のヒント
「約数」の学習のときに、この「ダース」の話をしてみると、子どもたちはより身近に感じるかもしれません。「どうして12個でひとまとまりにするのかな?」という問いかけをしてみると、分ける人数の多さ(約数の多さ)に気づけるはずです。


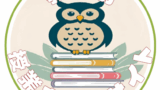
コメント