※Word文書をプレビューで表示している場合、表記にズレが生じる可能性があります。
データをダウンロードした際には正しく表記されます。
縄文時代
『とる』時代(採る・捕る)
魚や貝をとって食べていた。(貝塚)
石器を用いて、イノシシやマンモスを飼っていた。
⇒命の危険がある。とれない時がある。⇒自分たちでつくる時代へ
弥生時代
『つくる』時代
米をつくる・稲作(中国から伝わる)
動物を飼う
⇒作ったものを保存する必要がある⇒保管物の奪い合いが発生する⇒人対人の戦い⇒リーダーが必要となる
古墳時代
『名声』の時代
保管物を守るためには、大人数の方が強い⇒少人数集団が合体し始める
リーダーが名声を持つ⇒しかし、いつかは死ぬ⇒死後も名声を保ちたい⇒大きな墓(古墳)を作ることで、死後も名声を!
集団の人数が増加したことでルールを決める必要が出てきた。
飛鳥時代
『きまり』の時代
大人数をまとめるためにルールが必要。天皇を中心に集団のルールを作った。
仏教を活用した政治
貴族が力をつける。
奈良時代
『権力争い』の時代
地方分権が進み、貴族が華やかな暮らしをする時代。一方で、貴族同士の争いも多くあった。
平安時代
『優雅』な時代
貴族が華やかで優雅に暮らしていた。
貴族のボディーガードを務めた武士が力をつけ始める。武士が政治に関与し始める。


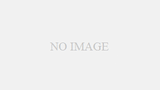
コメント